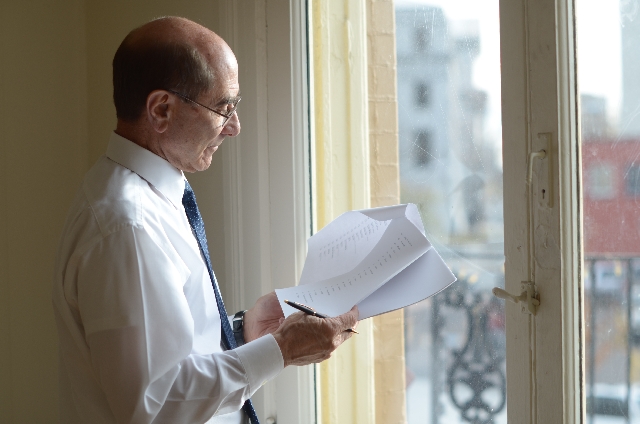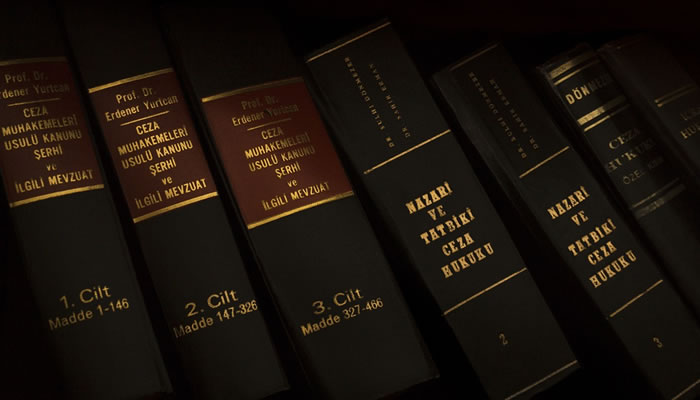営利・非営利を問わず、多数決ではない有益な合意形成をするためには、プロセスと意見の分類に対する理解が必要。そのためのガイドラインを提示する。

<プロセス>
参加者全員にプロセスを共有し、進捗状況が分かるようにする。
合意形成にいたらなかった場合はトップダウンで決定するなど、先延ばしを防ぐためのルールも決めておく。
<意見の分類>
合意形成とは参加者全員の利害を満たすことを意味する。
議論全体、特に図のプロセス5において、参加者の意見一つひとつの意味を全員が理解できるようになると、合意形成に成功する。
多くの会議は生産性が低い。
発言すれば責任を追及される、否定的な意見を述べるとあとでしっぺ返しを食うなど、硬直化しがちだ。
その原因の一つは、我々が合意形成の仕組みを教わったことがないからだと考えられる。
まず、合意形成のプロセスを確認していただきたい。
1. 司会・参加メンバー・スケジュール・注意事項の確認
社外のメンバーが参加する場合は、特に参加メンバーを紹介が重要。
2. 合意したいテーマの確認
報告や意見収集ではなく、合意したいという強い意思表示が必要。
3. 参加者の権限・役割・判断基準・利害の確認
本来は各部門、機関の責任者が出席するべきだが、代理出席の場合はその旨を伝える。(権限移譲されていなければその場で電話確認できるようにしておく)
判断基準や利害は、それぞれが異なるため、司会は事前にヒアリングしホワイトボードに書き出す、資料で渡すなどの準備をする。
4. 司会から合意試案と策定の経緯説明
合意の最終案を作るために試案(たたき台)を提示し、その案に至った経緯を説明する。
参加者はその経緯を知った上での発言が可能になる。
5. 参加者全員から意見収集
合意形成は多数決を取るためのものではない。
あくまでも参加者全員の意見を得て、ベストアンサーを出すことが目的である。(図:意見の分類を使用すると良い)
6. ドラフトの策定
試案から意見を元に合意の一歩手前のドラフトを作り、この時点で合意を得る。
7. 課題想定、詳細検討
合意された場合、対外的にどのような影響があるかを、全員が一歩引いて検証する。
追加で調査が必要なら、最終合意はせず次回に持ち越すなどが必要。
8. 合意形成
合意の文面を作り、全員で署名するなどする。
9. 具体的行動の決定
誰が何をいつまでに、の原則にのっとって、実行に移す。
監視、監査、報告するためのルールも決めて、合意がもたらす成果を確実なものとする。
次に、意見の分類を確認して欲しい。
すべての発言が「全員の利害を満たすアイデア」であることが望ましいが、実際にはその他の意見の方が多い。
この分類表を見ながら意見・発言を仕分けしていくことで、参加者全員の発言の質を向上させる。
不適切な意見があれば司会が「それは○○ですね?」「○○な意見はありませんか?」などと確認し、合意形成への悪影響を防ぐ。
・全員の利害を満たすアイデア
プロセス5での発言は、原則このアイデアに限定するべきだ。
・事例/統計
専門外でないことには誰も判断ができない。そこで合意に必要な事例や統計などのデータを提示することも重要。
司会が自分で用意するか、参加者に事前に依頼しておく。
・未来予測
事例/統計に類似するが、参加者が知っておいた方がいい未来に関する情報があれば有益だ。
・対案がある批判
誰かの発言、アイデアを批判する場合は、必ず対案を求める。
対案なき批判は、知識や権限の誇示を目的としたもので、合意形成には役立たない。
・妥協案
合意形成とは似て非なるものだが、妥協しませんかと提案することで後ろ向きな案となってしまう。
全員の利害を満たすアイデアだと提示できる方が望ましい。
・ただの批判
事例や統計を示すだけならいいが、自分の評価を発言するだけ、他者の発言のミス指摘や上げ足を取るなどの行為は、慎むべきである。
発言があった場合は、司会が対案を求める、なければただの批判であると参加者に知らしめ悪影響を防ぐ。
・価値観の追求
なぜそう思うのか、誰が責任を取るのか、など、合意形成とは関係のない発言は排除したい。
司会より、価値観を問う質問はご遠慮ください、と止めないと余計な議論が展開されてしまいかねない。
・過去の失敗
過去に同じ決定をしたことがある、というのは事例としては有益だが、だから私はダメだと思うという発言は避けてもらいたい。
過去の発言をするのは、責任を自分が取りたくないというだけの方が多い。
・余談
場を和ませたいということでユーモアある発言をする人がいる。マイナスではないが、思考の糸が切れてしまうので、できれば避けたい。
そういう発言が出た場合は休憩を入れる必要があるというサインかも知れない。
以上。ガイドラインとして様々な役割の方に活用していただき、日本経済活性化、生産性向上に役立てていただきたい。
資料のダウンロードはこちら
合意形成ガイドライン